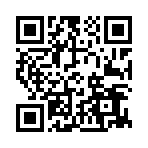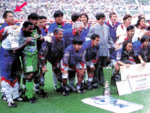グンブロ広告
ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月
 お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。
お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2017年10月31日
インテルミラノの長友選手の体幹トレーニングに挑戦してみました!
サッカーセリエAのインテルミラノ所属の長友佑都選手。
体幹トレーニングを熱心に取り入れていることでも有名です。
その長友選手が、自身の経営する会社Cuore(クオーレ)で輸入販売する体幹トレーニング器具が
FLOWIN(フローイン)。
そのFLOWINで長友選手が行っているトレーニングの一つを、
私自身やってみました。
まずは、どんなトレーニングかというと、
下の「長友佑都の体幹・腹筋トレーニング」というyoutube動画の1分33秒あたりから
長友選手が行っているエクササイズです。
前半のエクササイズをMountain Climber、後半のエクササイズをProne Pikeと呼ぶらしいです。
私が行っているMountain Climber&Prone Pikeの動画は長くて、
撮影した携帯からパソコンへ一遍に全てを送れないので、
動画を前半後半に分けました。
Mountain Climberを30歩ほど、Prone Pikeを10回やったところまでです。
後で見直すと、長友選手はMountain Climberを20歩ほどしかやっていなかったので、
多すぎたようです。
その分、スピードが遅めです。
前半のProne Pikeが終わったところから、
続けてやったMountain Climberを35歩とProne Pike10回の動画です。
呼吸が荒くなっているのがわかりますが、
試しとはいえ、休みなしの2セットはやり過ぎました。
ペースも落ち、動きも小さくなっています。
終わった後、気持ち悪くなりました。
明らかな酸欠です。
次やるときは、Mountain Climber20歩&Prone Pike10回がちょうど良さそうです。
レベルの高いアスリートの強化のためには動きを速くするのもいいのですが、
純粋に体幹(コア)だけの機能を高めたければ、
コアの使い方に意識を集中してゆっくりとした動きでやることをオススメします。
体幹トレーニングを熱心に取り入れていることでも有名です。
その長友選手が、自身の経営する会社Cuore(クオーレ)で輸入販売する体幹トレーニング器具が
FLOWIN(フローイン)。
そのFLOWINで長友選手が行っているトレーニングの一つを、
私自身やってみました。
まずは、どんなトレーニングかというと、
下の「長友佑都の体幹・腹筋トレーニング」というyoutube動画の1分33秒あたりから
長友選手が行っているエクササイズです。
前半のエクササイズをMountain Climber、後半のエクササイズをProne Pikeと呼ぶらしいです。
私が行っているMountain Climber&Prone Pikeの動画は長くて、
撮影した携帯からパソコンへ一遍に全てを送れないので、
動画を前半後半に分けました。
Mountain Climberを30歩ほど、Prone Pikeを10回やったところまでです。
後で見直すと、長友選手はMountain Climberを20歩ほどしかやっていなかったので、
多すぎたようです。
その分、スピードが遅めです。
前半のProne Pikeが終わったところから、
続けてやったMountain Climberを35歩とProne Pike10回の動画です。
呼吸が荒くなっているのがわかりますが、
試しとはいえ、休みなしの2セットはやり過ぎました。
ペースも落ち、動きも小さくなっています。
終わった後、気持ち悪くなりました。
明らかな酸欠です。
次やるときは、Mountain Climber20歩&Prone Pike10回がちょうど良さそうです。
レベルの高いアスリートの強化のためには動きを速くするのもいいのですが、
純粋に体幹(コア)だけの機能を高めたければ、
コアの使い方に意識を集中してゆっくりとした動きでやることをオススメします。
2012年01月16日
遊びの大切さ 外反(扁平)足の男の子
うちの最も年少のクライアントは小1のY.Kちゃんです。
Y.Kちゃんのおばあさんが、
整形外科で『外反足首病』と言われ、 ※1
どんな運動をさせたら良いのかと
相談してきた事がきっかけでした。
『外反足首病』と言う語は聞いた事がなかったのですが、
子供に多い外反(扁平)足のことだろうと考えました。
おばあさんは、Y.Kちゃんが「運動が苦手」で
「運動嫌い」なのでどうしたら良いのかともおっしゃっていました。
私は、まだ小さい子供の場合、
足の筋肉等が発達して外反(扁平)が軽減する可能性があるので、
適切な運動を行なわせることがまず大切で、
そんなに心配する事はないだろうと伝えました。
また、子供というのはリハビリや運動処方で
大人にやらせる様な"◯◯の為の運動”といった型にはまった運動は
やらせることは無理である、
本来子供は楽しい遊びであれば身体を使った運動も大好きになることを
お伝えしました。
つまり、こちら(大人側)は足の筋や関節の発達を促す様な内容を
"楽しい”遊びとして子供に与えれば、
外反(扁平)足を矯正する様な運動を
Y.Kちゃんにもさせる事が出来るであろうと言う見通しを話しました。
そして、結局そのような運動を考え与える役割を
私が引き受ける事になりました。
私が与えている運動の内容は、
体幹部の発達を促す運動、
股関節の運動、
足部の運動、
それらが統合された運動で構成されています。
例えば、マット上で転がったり、
バランスボールなどで遊んだり、
はいはいしたり、
膝の上に直立して歩いたり、
踵を挙げてつま先立ちで歩いたり、
片脚立ちでバランスをとったり、
ケンケンや両足とびをしたり、
そんなことです。
今年最初の回では、
ボール(ソフトギムニク)を投げ落として空中で蹴る遊びをしたところ、
タイミングを合わせられず足の甲で蹴れなかったので、
こちらの投げたボールを両手でキャッチしてから
両手で投げ返す遊びをしてもらいました。 ※2
Y.Kちゃんがボールを両手で投げ返す時、
膝が伸び切ったままで上手く投げられなかったので、
膝の屈伸を使って投げることを教えたら、
10球程でも見違えて上手になりました。
(この技術が一度で定着するとは限りませんが。)
そんな程度の運動内容だったりします。
それでも、Y.Kちゃんが楽しみながら変わってくれる事に
大きな意義があると思っています。
このエピソードでわかるように、
Y.Kちゃんはとても運動経験が少なかったのです。
だから運動技能が拙いのです。
そして運動する意欲が育ちにくかったのです。
私はそこを変える事が、
外反(扁平)足にのみ着目して運動処方するよりも
とても大事な事だと思っています。
週1回ずつやり3ヶ月目に入りましたが、
スイミングでバタ足が上達したり、
走ることや運動全体に自信が出てきて、
前よりも身体を動かすようになったそうです。
肝心な外反(扁平)足は、
もちろんそんな短期間で大きな変化はありませんし、
効果を急いで求める必要もありません。
うちに通う日以外でも、
おばあちゃんと一緒に"遊んでいる”ということに
価値があると思っています。
Y.Kちゃんは、私がテーピングした最年少者でもあります。
運動前に足にテーピングをして、
運動中過度に外反しないように制限しています。
小さい子供なのですぐに「テープを貼ったところが痛い」と言いますから、
痛く無いように確認しながら出来るだけ軽く弱く、
それでいて効果があるようにテーピングします。
一度でOKが出る事はなく、
いつも2〜3度やり直ししないとテーピングが完成しません。
まだ、ジャンプなどの足に強い力がかかる運動は、
時々痛そうにする事があるので、
しばらくはテーピングの補助はかかせません。
※1 外反足首病
やはり、正式にはこんな病名はありません。
最初にかかった整形外科の先生の造語?かと思われます。
1月最初の運動の時、違う整形外科で指摘されたそうです。
外反足や外反扁平足と呼ぶ事が一般的だと思います。
※2 足の甲で蹴れなかったので〜してもらいました。
ボールの空中で動き(軌道)に慣れてもらう意図もある。
足の甲で蹴るのは、片足での支持力アップや、
ボールを蹴る時の足の甲の感覚を覚えてもらいたかったから。
Y.Kちゃんのおばあさんが、
整形外科で『外反足首病』と言われ、 ※1
どんな運動をさせたら良いのかと
相談してきた事がきっかけでした。
『外反足首病』と言う語は聞いた事がなかったのですが、
子供に多い外反(扁平)足のことだろうと考えました。
おばあさんは、Y.Kちゃんが「運動が苦手」で
「運動嫌い」なのでどうしたら良いのかともおっしゃっていました。
私は、まだ小さい子供の場合、
足の筋肉等が発達して外反(扁平)が軽減する可能性があるので、
適切な運動を行なわせることがまず大切で、
そんなに心配する事はないだろうと伝えました。
また、子供というのはリハビリや運動処方で
大人にやらせる様な"◯◯の為の運動”といった型にはまった運動は
やらせることは無理である、
本来子供は楽しい遊びであれば身体を使った運動も大好きになることを
お伝えしました。
つまり、こちら(大人側)は足の筋や関節の発達を促す様な内容を
"楽しい”遊びとして子供に与えれば、
外反(扁平)足を矯正する様な運動を
Y.Kちゃんにもさせる事が出来るであろうと言う見通しを話しました。
そして、結局そのような運動を考え与える役割を
私が引き受ける事になりました。
私が与えている運動の内容は、
体幹部の発達を促す運動、
股関節の運動、
足部の運動、
それらが統合された運動で構成されています。
例えば、マット上で転がったり、
バランスボールなどで遊んだり、
はいはいしたり、
膝の上に直立して歩いたり、
踵を挙げてつま先立ちで歩いたり、
片脚立ちでバランスをとったり、
ケンケンや両足とびをしたり、
そんなことです。
今年最初の回では、
ボール(ソフトギムニク)を投げ落として空中で蹴る遊びをしたところ、
タイミングを合わせられず足の甲で蹴れなかったので、
こちらの投げたボールを両手でキャッチしてから
両手で投げ返す遊びをしてもらいました。 ※2
Y.Kちゃんがボールを両手で投げ返す時、
膝が伸び切ったままで上手く投げられなかったので、
膝の屈伸を使って投げることを教えたら、
10球程でも見違えて上手になりました。
(この技術が一度で定着するとは限りませんが。)
そんな程度の運動内容だったりします。
それでも、Y.Kちゃんが楽しみながら変わってくれる事に
大きな意義があると思っています。
このエピソードでわかるように、
Y.Kちゃんはとても運動経験が少なかったのです。
だから運動技能が拙いのです。
そして運動する意欲が育ちにくかったのです。
私はそこを変える事が、
外反(扁平)足にのみ着目して運動処方するよりも
とても大事な事だと思っています。
週1回ずつやり3ヶ月目に入りましたが、
スイミングでバタ足が上達したり、
走ることや運動全体に自信が出てきて、
前よりも身体を動かすようになったそうです。
肝心な外反(扁平)足は、
もちろんそんな短期間で大きな変化はありませんし、
効果を急いで求める必要もありません。
うちに通う日以外でも、
おばあちゃんと一緒に"遊んでいる”ということに
価値があると思っています。
Y.Kちゃんは、私がテーピングした最年少者でもあります。
運動前に足にテーピングをして、
運動中過度に外反しないように制限しています。
小さい子供なのですぐに「テープを貼ったところが痛い」と言いますから、
痛く無いように確認しながら出来るだけ軽く弱く、
それでいて効果があるようにテーピングします。
一度でOKが出る事はなく、
いつも2〜3度やり直ししないとテーピングが完成しません。
まだ、ジャンプなどの足に強い力がかかる運動は、
時々痛そうにする事があるので、
しばらくはテーピングの補助はかかせません。
※1 外反足首病
やはり、正式にはこんな病名はありません。
最初にかかった整形外科の先生の造語?かと思われます。
1月最初の運動の時、違う整形外科で指摘されたそうです。
外反足や外反扁平足と呼ぶ事が一般的だと思います。
※2 足の甲で蹴れなかったので〜してもらいました。
ボールの空中で動き(軌道)に慣れてもらう意図もある。
足の甲で蹴るのは、片足での支持力アップや、
ボールを蹴る時の足の甲の感覚を覚えてもらいたかったから。
2011年01月11日
『姿勢改善のためのエクササイズ教室』に手応えあり
昨日、今年最初の『姿勢改善のためのエクササイズ教室』を開きました。
今月(今年)から、平日の昼間にも開催することにして、
昨日は午後2時からと午後7時からの2回開催しました。
午後2時からは、マッサージにも通っていただいているTさん(女性)と
その妹のYさんのお二人が参加されました。
Tさんは4回目、Yさんは初めての参加なので、
Tさんにとっては復習のような感じになったかとは思います。
でも、大事なポイントは、何回も繰り返す価値があります。
午後7時からの参加者は、
やはり治療に通っている音楽家のKさんとその教え子のHさん、
そしてお一人で申し込んでくれたSさんの3人で、
3人とも女性で初参加でした。
内容は、初参加の方が多かったので、昼の部も夜の部も、
ほとんど同じ内容でした。
講習中私が説明するのは、
立ってのエクササイズはほとんど "ダンス"だと言うこと。
それもすごく簡単な初歩的な "ダンス"。
難しく考えず、楽しくノッてもらいます。
楽しんでリラックスして頂いた方が、動きが良くなります。
2回の『教室』とも、笑い声が良く出ていたので、
楽しんでいただけたと自負しています。
(実際、そのように言っていただいて、喜んでいます。)
Tさんは、東京のお知り合いの方に話されたら、
東京でこの『教室』を開いて欲しいと言う話も持ち上がりました。
時間的な問題、費用の問題等、クリアしなければいけないことがありますが、
東京出張教室が実現できればいいなと思っています。
今月の残りの『教室』の予定
1月20日(木) ①午後2時〜3時(現在予約1名) ②午後7時〜8時
1月24日(月) ①午後1時〜3時 ②午後7時〜8時
各教室の2時間前までにご予約ください。
予約申し込みは、
治療室ボディ・インスピレーション
高崎市緑町4−7−7 楽歩堂靴店ビル内
TEL 027-364-1072 まで、
今月(今年)から、平日の昼間にも開催することにして、
昨日は午後2時からと午後7時からの2回開催しました。
午後2時からは、マッサージにも通っていただいているTさん(女性)と
その妹のYさんのお二人が参加されました。
Tさんは4回目、Yさんは初めての参加なので、
Tさんにとっては復習のような感じになったかとは思います。
でも、大事なポイントは、何回も繰り返す価値があります。
午後7時からの参加者は、
やはり治療に通っている音楽家のKさんとその教え子のHさん、
そしてお一人で申し込んでくれたSさんの3人で、
3人とも女性で初参加でした。
内容は、初参加の方が多かったので、昼の部も夜の部も、
ほとんど同じ内容でした。
講習中私が説明するのは、
立ってのエクササイズはほとんど "ダンス"だと言うこと。
それもすごく簡単な初歩的な "ダンス"。
難しく考えず、楽しくノッてもらいます。
楽しんでリラックスして頂いた方が、動きが良くなります。
2回の『教室』とも、笑い声が良く出ていたので、
楽しんでいただけたと自負しています。
(実際、そのように言っていただいて、喜んでいます。)
Tさんは、東京のお知り合いの方に話されたら、
東京でこの『教室』を開いて欲しいと言う話も持ち上がりました。
時間的な問題、費用の問題等、クリアしなければいけないことがありますが、
東京出張教室が実現できればいいなと思っています。
今月の残りの『教室』の予定
1月20日(木) ①午後2時〜3時(現在予約1名) ②午後7時〜8時
1月24日(月) ①午後1時〜3時 ②午後7時〜8時
各教室の2時間前までにご予約ください。
予約申し込みは、
治療室ボディ・インスピレーション
高崎市緑町4−7−7 楽歩堂靴店ビル内
TEL 027-364-1072 まで、
2010年07月21日
子供の運動は多様性と楽しさが大切
ちょっと古い話ですが、群馬テレビで放送した
全日本少年サッカー大会の群馬県予選会の決勝戦を
録画して観戦しました。
ちょっと嫌だったのは、
片方のチームに2人くらい変な走り方をする子がいたこと。
膝が上がらず、脚を引きずるような走り方で、
当然あまり速くありません。(はっきり言って遅い。)
フリーのボールを追いかけて競る時は、
そんなフォームで無理矢理でもスピードを上げようと頑張るから、
余計に腰などに無理な負荷がかかるようで心配です。
始めは怪我でもしているのかと思いましたが、
2人も同じような子がいて
それぞれ好守の中心選手らしく、
確か二人ともフル出場しているので、
怪我ではなくそういう走り方なのでしょう。
このチームは足元の技術が高く、
結局優勝したのですが、
サッカーの個人技を伸ばすのは良いのですが、
基本的な運動技術である走技術を観ていないのかと疑問に思いました。
小学生のうちにあんな走り方で固まってしまったら、
近い将来サッカーにも大きく影響するはずです。
腰にも負担がかかります。
また、もう片方のチームは、
ディフェンスの時に相手の身体に手を回し、
シャツを掴んでばかりいました。
子供のうちから、こんな小手先のことを教えていたら、
多くのスポーツに共通する身体感覚や身体操作のスキルを
身に付けられないのではないかと思います。
(掴むことを教えると、手にばかり神経が集中してしまう。)
大人(コーチ)は、子供のうちは、サッカー技術だけでなく、
様々な運動技術や体力要素を伸ばせるように、
子供達全員に目を配り、
多彩な運動メニューを組み、
全面的な発育を促せるように配慮して
子供達を一人一人導くことを至上命題としてもらいたい。
ある高崎市内の小学校の先生から、
2年生の親子対象に『親子運動教室(仮題)』の講師を依頼されました。
小2の体力はどのくらいか、
それ以上に親の体力はどのくらいなのか、
またお父さんだけなのか、お母さんだけなのか、混合なのか、
そんなことを考えながら、
多彩で楽しい運動を提案してみたいと思っています。
依頼した先生は、前任校で
私がPTA(1年生のお母さん方)対象のストレッチング教室や
サッカー部または女子卓球部に行ったストレッチング教室を知っていて、
ストレッチング中心にと考えていたようですが、
本格的なストレッチングは小2には難しく、
柔軟性を高める運動も念頭に置いて考えていきたいと思っています。
フランスのカイヨワが分類した遊びの4つの要素
アゴン(競争)、アレア(偶然)、
ミミクリー(模倣、イリングス(めまい)
を取り入れたいと思います。
また、コーディネーショントレーニングの考え方も取り入れて
面白い無いようになるように工夫したいと思っています。
予定されている9月までに
いろいろと考える楽しみができました。
全日本少年サッカー大会の群馬県予選会の決勝戦を
録画して観戦しました。
ちょっと嫌だったのは、
片方のチームに2人くらい変な走り方をする子がいたこと。
膝が上がらず、脚を引きずるような走り方で、
当然あまり速くありません。(はっきり言って遅い。)
フリーのボールを追いかけて競る時は、
そんなフォームで無理矢理でもスピードを上げようと頑張るから、
余計に腰などに無理な負荷がかかるようで心配です。
始めは怪我でもしているのかと思いましたが、
2人も同じような子がいて
それぞれ好守の中心選手らしく、
確か二人ともフル出場しているので、
怪我ではなくそういう走り方なのでしょう。
このチームは足元の技術が高く、
結局優勝したのですが、
サッカーの個人技を伸ばすのは良いのですが、
基本的な運動技術である走技術を観ていないのかと疑問に思いました。
小学生のうちにあんな走り方で固まってしまったら、
近い将来サッカーにも大きく影響するはずです。
腰にも負担がかかります。
また、もう片方のチームは、
ディフェンスの時に相手の身体に手を回し、
シャツを掴んでばかりいました。
子供のうちから、こんな小手先のことを教えていたら、
多くのスポーツに共通する身体感覚や身体操作のスキルを
身に付けられないのではないかと思います。
(掴むことを教えると、手にばかり神経が集中してしまう。)
大人(コーチ)は、子供のうちは、サッカー技術だけでなく、
様々な運動技術や体力要素を伸ばせるように、
子供達全員に目を配り、
多彩な運動メニューを組み、
全面的な発育を促せるように配慮して
子供達を一人一人導くことを至上命題としてもらいたい。
ある高崎市内の小学校の先生から、
2年生の親子対象に『親子運動教室(仮題)』の講師を依頼されました。
小2の体力はどのくらいか、
それ以上に親の体力はどのくらいなのか、
またお父さんだけなのか、お母さんだけなのか、混合なのか、
そんなことを考えながら、
多彩で楽しい運動を提案してみたいと思っています。
依頼した先生は、前任校で
私がPTA(1年生のお母さん方)対象のストレッチング教室や
サッカー部または女子卓球部に行ったストレッチング教室を知っていて、
ストレッチング中心にと考えていたようですが、
本格的なストレッチングは小2には難しく、
柔軟性を高める運動も念頭に置いて考えていきたいと思っています。
フランスのカイヨワが分類した遊びの4つの要素
アゴン(競争)、アレア(偶然)、
ミミクリー(模倣、イリングス(めまい)
を取り入れたいと思います。
また、コーディネーショントレーニングの考え方も取り入れて
面白い無いようになるように工夫したいと思っています。
予定されている9月までに
いろいろと考える楽しみができました。