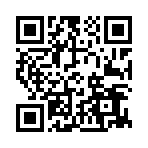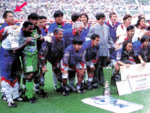グンブロ広告
ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月
 お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。
お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2010年10月25日
日常生活に潜む腰痛の原因
腰痛(私の場合は股関節周辺・臀部を含めている)で来室される方は多くいます。
中には深刻に悩んでいらっしゃる方もいます。
私は、全身マッサージを
全身の筋肉や皮膚の状態をチェックすることも兼ねて行なっています。
「原因は何でしょう?」とお客さんに聞かれることもよく有りますが、
大抵私は「何ででしょうね?」と答えるしかありません。
「ここやここの筋肉が硬く緊張している(張っている)と
腰痛が起こりやすいのですが、
何故この筋肉が硬く緊張してしまうのかは一概には言えません。」
と説明します。
原因は一つとは限りません。
だから、原因となりそうな姿勢や行動がないかをこと細かく聞いていくのです。
いろいろな方の仕事や日常生活についてあれこれ聞いているうちに
知ったことも有ります。
例えば、お医者さんというのは、
無理な体勢で診察や治療や手術を行なっていることが多いということ。
歯科医は皆偏った変な体勢での仕事を強いられているし、
眼科医も小さな細かいものを視るので大変だし、
学校での児童・生徒の集団検診に携わっていると
大変な人数を一遍に診なければいけないし、
耳鼻科の大学病院の先生は
無理な姿勢で狭い部位に細かな手術をするので大変疲れるとおっしゃっていたし、
内科や外科の医師も座りっぱなしで大変だし、
低い診察台に横になった患者を覗き込んだり処置するのは腰に負担がかかるし、
とにかくお医者さんも大変だなとつくづく感じさせられています。
日常のどんな行動が腰に負担をかけているのかということも、
人によって様々です。
ある方は炊事、特キッチン台でのあれこれ仕事することが
一番腰痛の症状を引き起こしていることがわかりました。
また、ある方は、家事の済んだ昼食後から夕食の支度までの数時間、
掘りゴタツに座って大好きな読書をしていることが
一番原因として疑わしいことが判明しました。
特にこの時期は、暖かいお昼後と同じ状態で一つ処にいると、
4時をまわる頃には冷えてきてしまいます。
また、掘りゴタツに座っていると両足がぶらぶらし、
体をしっかりと固定できないことも姿勢が崩れる原因になり、
ひいては腰痛の原因となります。
一人ひとり仕事や生活上の姿勢・行動が違いますから、
その異なる原因を追求することが
治療と予防には大切だと思います。
そして、その原因の追求は自分自身で振り返ることから始まります。
我々セラピストは、それ手助けできるだけなのです。
だから、しっかりとお客さんの話を聞かなければならないと思います。
中には深刻に悩んでいらっしゃる方もいます。
私は、全身マッサージを
全身の筋肉や皮膚の状態をチェックすることも兼ねて行なっています。
「原因は何でしょう?」とお客さんに聞かれることもよく有りますが、
大抵私は「何ででしょうね?」と答えるしかありません。
「ここやここの筋肉が硬く緊張している(張っている)と
腰痛が起こりやすいのですが、
何故この筋肉が硬く緊張してしまうのかは一概には言えません。」
と説明します。
原因は一つとは限りません。
だから、原因となりそうな姿勢や行動がないかをこと細かく聞いていくのです。
いろいろな方の仕事や日常生活についてあれこれ聞いているうちに
知ったことも有ります。
例えば、お医者さんというのは、
無理な体勢で診察や治療や手術を行なっていることが多いということ。
歯科医は皆偏った変な体勢での仕事を強いられているし、
眼科医も小さな細かいものを視るので大変だし、
学校での児童・生徒の集団検診に携わっていると
大変な人数を一遍に診なければいけないし、
耳鼻科の大学病院の先生は
無理な姿勢で狭い部位に細かな手術をするので大変疲れるとおっしゃっていたし、
内科や外科の医師も座りっぱなしで大変だし、
低い診察台に横になった患者を覗き込んだり処置するのは腰に負担がかかるし、
とにかくお医者さんも大変だなとつくづく感じさせられています。
日常のどんな行動が腰に負担をかけているのかということも、
人によって様々です。
ある方は炊事、特キッチン台でのあれこれ仕事することが
一番腰痛の症状を引き起こしていることがわかりました。
また、ある方は、家事の済んだ昼食後から夕食の支度までの数時間、
掘りゴタツに座って大好きな読書をしていることが
一番原因として疑わしいことが判明しました。
特にこの時期は、暖かいお昼後と同じ状態で一つ処にいると、
4時をまわる頃には冷えてきてしまいます。
また、掘りゴタツに座っていると両足がぶらぶらし、
体をしっかりと固定できないことも姿勢が崩れる原因になり、
ひいては腰痛の原因となります。
一人ひとり仕事や生活上の姿勢・行動が違いますから、
その異なる原因を追求することが
治療と予防には大切だと思います。
そして、その原因の追求は自分自身で振り返ることから始まります。
我々セラピストは、それ手助けできるだけなのです。
だから、しっかりとお客さんの話を聞かなければならないと思います。
2010年10月18日
PTA親子レクリエーション教室(小2)本番
高崎市内の小学校から依頼された『親子運動教室(仮題)』。
(実際には『親子リクリエーション教室』であったようです。)
前々回に、そのリハーサル(のようなこと)をしたと書きましたが、
9月30日(木)に本番が行なわれました。
(ちょっと古い話になってしまいました。)
PTAの行事ということで、
役員のお母さん方が案内をしてくれました。
初め、玄関で待ち受けてくれて、
そのまま控え室(校長室)に案内されました。
少しお話をしてから、10分前に会場である体育館に移動しました。 ※1
既に子供達は整列していて、親もほとんど集まっていました。
まずは、私が見本となってストレッチングや体操を行なってから、
親子で組んでの運動を展開していきました。
初めは、親子で向かい合ってピョン、ピョン、と2回ジャンプして、
3回目のジャンプの着地で親が様々なポーズをとります。
例えば、両脚を前後や左右に開いたり、
両手を挙げたりといった単純なポーズです。
子供はそのポーズを素早く真似してポーズをとってもらうゲームです。
ピョン、ピョン、パッ(ポーズ)、ウン(休止)と4拍子で
次々とポーズを変えて続けます。
子供達も、観てから真似するだけでなく、
続けていると次のポーズを予想しますから、
予想が外れたりポーズがおかしいと笑い声があちこちから上がりました。
続けて、子供がポーズを出題するように変えてみましたが、
小2の子供でも様々なアイディアを出してきて、
大いに盛り上がりました。
次に、組み体操のように親子で様々な動きをしてもらいました。
例えば背中合せに長座姿勢で座り
お互いに両手を後ろで組んだまま立ち上がる。
親が子供をおんぶしたり肩車したりしたまま
親→子共の順に両手を(体から離して)上に挙げる。
向かい合ってお互いに両手をつないだまま
親は膝を曲げて腰を下ろし、
子供が親の太腿の上に載って立つ。
親が子供をおんぶし、
子供は親にぶら下がったまま(床に降りず)
親の体を1周回って背中に戻る。
(親は手で子供を持ってはいけないが、体勢を変えて助けて良い。)
これらの運動では、
親には子供の体重や大きさ(成長)を体で感じてもらい、
子供には自分の体を支える力を着けてもらい、
さらに親子で息を合わせる・協力し合うことが目的となります。
この他にも、
親子で先に相手のお尻や背中をタッチした方が勝ちとするゲーム
(親はハンディとして、何時もどちらかの手を床に着けたまま)、
親子でボールを転がしたり投げてキャッチボールなどをしました。 ※2
(ここに書いたのは、実際にやったことの一部ですし、
アイディアはその何倍も準備してありました。)
親子でいっしょにやるということは、
親子で競争したり、
親子で協力したりして、
親子で(文字通り)触れ合ったり、
親子で楽しむことに意味があります。
教室後のPTA役員さんの言葉でも、
小2ともなると、だんだん親子でスキンシップすることや
遊ぶことが減っていることが伺えます。
幼稚園の頃には子供が小さすぎたり力が足りなくてできない運動、
小学校中学年では、子供が大きく重くなり過ぎてできない運動、
高学年になると子供の体力が高くなり親の体力を上回ったり
もう照れくさくて親とはやり難い運動も出てきます。
小2だからできること、小2の今しかできないかも知れないこと、
そうした運動(遊び)を考える手助けが、
少しでもできたのではないかな(できたらいいな)と思っています。
帰りに学校の玄関で、
「ありがとうございました。」と
元気に挨拶してくれた小2の女の子がいました。
とても良い気持ちで、小学校から帰ることができました。
(小学校でも中学校でもどちらでも結構ですので、
何か運動に関係する行事に指導者が必要でしたら、
何でも相談して欲しいと思っています。
このブログを読んでいる方、よろしくお願いします!)
※1 控え室(校長室)に案内され~会場~に移動しました
小中学校の行事に呼ばれる時は、大体こんなパターンが多かった。
ただし、今までは、応対してくれるのが、
先生であることが多かった。
中学校の部活で呼ばれる場合は、
現場に直行する場合がほとんどである。
※2 親子でボールを転がしたり投げてキャッチボール
次々にルールを変えてやると楽しいし、
子供のコーディネーション能力を高めることができる。
例えば、両手キャッチから片手キャッチへとルールを変える。
手ではなく足の裏でボールを止める。
後ろ向きになって股の間から転がるボールをキャッチする。
投げる場合もワンバウンドしてから捕るのか、
ノーバウンドで捕るのかなど変化をつける。
相手が投げてからキャッチするまでの間に
両手を(1~3回)叩く、
その場で1回まわる、
野菜や果物の名前を言う、、、etc。
こうしたルールは親子で考えても楽しいだろう。
(実際には『親子リクリエーション教室』であったようです。)
前々回に、そのリハーサル(のようなこと)をしたと書きましたが、
9月30日(木)に本番が行なわれました。
(ちょっと古い話になってしまいました。)
PTAの行事ということで、
役員のお母さん方が案内をしてくれました。
初め、玄関で待ち受けてくれて、
そのまま控え室(校長室)に案内されました。
少しお話をしてから、10分前に会場である体育館に移動しました。 ※1
既に子供達は整列していて、親もほとんど集まっていました。
まずは、私が見本となってストレッチングや体操を行なってから、
親子で組んでの運動を展開していきました。
初めは、親子で向かい合ってピョン、ピョン、と2回ジャンプして、
3回目のジャンプの着地で親が様々なポーズをとります。
例えば、両脚を前後や左右に開いたり、
両手を挙げたりといった単純なポーズです。
子供はそのポーズを素早く真似してポーズをとってもらうゲームです。
ピョン、ピョン、パッ(ポーズ)、ウン(休止)と4拍子で
次々とポーズを変えて続けます。
子供達も、観てから真似するだけでなく、
続けていると次のポーズを予想しますから、
予想が外れたりポーズがおかしいと笑い声があちこちから上がりました。
続けて、子供がポーズを出題するように変えてみましたが、
小2の子供でも様々なアイディアを出してきて、
大いに盛り上がりました。
次に、組み体操のように親子で様々な動きをしてもらいました。
例えば背中合せに長座姿勢で座り
お互いに両手を後ろで組んだまま立ち上がる。
親が子供をおんぶしたり肩車したりしたまま
親→子共の順に両手を(体から離して)上に挙げる。
向かい合ってお互いに両手をつないだまま
親は膝を曲げて腰を下ろし、
子供が親の太腿の上に載って立つ。
親が子供をおんぶし、
子供は親にぶら下がったまま(床に降りず)
親の体を1周回って背中に戻る。
(親は手で子供を持ってはいけないが、体勢を変えて助けて良い。)
これらの運動では、
親には子供の体重や大きさ(成長)を体で感じてもらい、
子供には自分の体を支える力を着けてもらい、
さらに親子で息を合わせる・協力し合うことが目的となります。
この他にも、
親子で先に相手のお尻や背中をタッチした方が勝ちとするゲーム
(親はハンディとして、何時もどちらかの手を床に着けたまま)、
親子でボールを転がしたり投げてキャッチボールなどをしました。 ※2
(ここに書いたのは、実際にやったことの一部ですし、
アイディアはその何倍も準備してありました。)
親子でいっしょにやるということは、
親子で競争したり、
親子で協力したりして、
親子で(文字通り)触れ合ったり、
親子で楽しむことに意味があります。
教室後のPTA役員さんの言葉でも、
小2ともなると、だんだん親子でスキンシップすることや
遊ぶことが減っていることが伺えます。
幼稚園の頃には子供が小さすぎたり力が足りなくてできない運動、
小学校中学年では、子供が大きく重くなり過ぎてできない運動、
高学年になると子供の体力が高くなり親の体力を上回ったり
もう照れくさくて親とはやり難い運動も出てきます。
小2だからできること、小2の今しかできないかも知れないこと、
そうした運動(遊び)を考える手助けが、
少しでもできたのではないかな(できたらいいな)と思っています。
帰りに学校の玄関で、
「ありがとうございました。」と
元気に挨拶してくれた小2の女の子がいました。
とても良い気持ちで、小学校から帰ることができました。
(小学校でも中学校でもどちらでも結構ですので、
何か運動に関係する行事に指導者が必要でしたら、
何でも相談して欲しいと思っています。
このブログを読んでいる方、よろしくお願いします!)
※1 控え室(校長室)に案内され~会場~に移動しました
小中学校の行事に呼ばれる時は、大体こんなパターンが多かった。
ただし、今までは、応対してくれるのが、
先生であることが多かった。
中学校の部活で呼ばれる場合は、
現場に直行する場合がほとんどである。
※2 親子でボールを転がしたり投げてキャッチボール
次々にルールを変えてやると楽しいし、
子供のコーディネーション能力を高めることができる。
例えば、両手キャッチから片手キャッチへとルールを変える。
手ではなく足の裏でボールを止める。
後ろ向きになって股の間から転がるボールをキャッチする。
投げる場合もワンバウンドしてから捕るのか、
ノーバウンドで捕るのかなど変化をつける。
相手が投げてからキャッチするまでの間に
両手を(1~3回)叩く、
その場で1回まわる、
野菜や果物の名前を言う、、、etc。
こうしたルールは親子で考えても楽しいだろう。