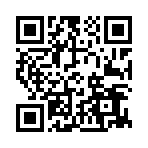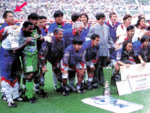グンブロ広告
ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月
 お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。
お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2017年10月15日
腹横筋、内・外腹斜筋をエコー画像で観察する
去る2月16日(木)に、祖師ヶ谷大蔵の「針灸指圧自然(じねん)堂」で、
中倉健院長と毎月恒例のエコー勉強会を行った時に撮影したエコー(超音波)画像です。。
毎回、どこの部位(筋)を観るかを話し合って進めるのですが、この時は私が
「Draw-inによる腹横筋及び内・外腹斜筋の筋厚変化」という論文(※1)をダウンロードして
読んでいたので、私自身の腹部で観察することにしました。
エコー画像は、論文に従い右腸骨両直上で前腋窩線状における横断面としました。
(だいたいおへそぐらいの高さで、腹直筋の右の脇腹です)
画像は、どれも右が正中線側(お腹の正面側)で、左が外側です。
画面の上が体表(皮膚)側で、下が奥(内臓側)になります。
筋肉は上にあるものから順に
外腹斜筋(緑)、内腹斜筋(黄緑)、腹横筋(赤)です。
左端にある目盛りと数字は、体表面からの距離を表しています。
1目盛りが1cmで、一番深くに見える数字の4は、4cmを表しています。
ですから、この画像は皮膚表面から4cmまでが写っていることになります。
 画像1
画像1
画像1は、安静時(筋収縮するような運動を行っていない時)の画像です。
それぞれの筋肉が収縮していない時の厚さがわかります。
 画像2
画像2
仰向けに寝た状態から、腹部をドローインだけをした時の画像です。
画像1と画像2を比較すると、
トランクカールした時の画像2は、外腹斜筋の収縮が見られ筋厚が厚くなっています。
内腹斜筋も少し収縮していますが、腹直筋の収縮はほとんど起きていません。
 画像3
画像3
仰向けに寝た状態から、腹部をドローインだけをした時の画像です。
ドローインのみを行った画像3では、外腹斜筋の収縮はほとんど見られず、
内腹斜筋と腹横筋、特に腹横筋の筋厚が大きくなり、
その収縮が大きいことがわかります。
これは、ドローインが腹横筋の収縮によって行われていることの証拠でもあるでしょう。
最後に、ドローインした時の内腹斜筋と腹横筋の収縮を確認できる動画を貼っておきます。
画像2は静止画でしたが、同じ時に撮った動画です。
https://www.youtube.com/watch?v=PlnUDQI1r6Q
中倉健院長と毎月恒例のエコー勉強会を行った時に撮影したエコー(超音波)画像です。。
毎回、どこの部位(筋)を観るかを話し合って進めるのですが、この時は私が
「Draw-inによる腹横筋及び内・外腹斜筋の筋厚変化」という論文(※1)をダウンロードして
読んでいたので、私自身の腹部で観察することにしました。
エコー画像は、論文に従い右腸骨両直上で前腋窩線状における横断面としました。
(だいたいおへそぐらいの高さで、腹直筋の右の脇腹です)
画像は、どれも右が正中線側(お腹の正面側)で、左が外側です。
画面の上が体表(皮膚)側で、下が奥(内臓側)になります。
筋肉は上にあるものから順に
外腹斜筋(緑)、内腹斜筋(黄緑)、腹横筋(赤)です。
左端にある目盛りと数字は、体表面からの距離を表しています。
1目盛りが1cmで、一番深くに見える数字の4は、4cmを表しています。
ですから、この画像は皮膚表面から4cmまでが写っていることになります。
 画像1
画像1画像1は、安静時(筋収縮するような運動を行っていない時)の画像です。
それぞれの筋肉が収縮していない時の厚さがわかります。
 画像2
画像2仰向けに寝た状態から、腹部をドローインだけをした時の画像です。
画像1と画像2を比較すると、
トランクカールした時の画像2は、外腹斜筋の収縮が見られ筋厚が厚くなっています。
内腹斜筋も少し収縮していますが、腹直筋の収縮はほとんど起きていません。
 画像3
画像3仰向けに寝た状態から、腹部をドローインだけをした時の画像です。
ドローインのみを行った画像3では、外腹斜筋の収縮はほとんど見られず、
内腹斜筋と腹横筋、特に腹横筋の筋厚が大きくなり、
その収縮が大きいことがわかります。
これは、ドローインが腹横筋の収縮によって行われていることの証拠でもあるでしょう。
最後に、ドローインした時の内腹斜筋と腹横筋の収縮を確認できる動画を貼っておきます。
画像2は静止画でしたが、同じ時に撮った動画です。
https://www.youtube.com/watch?v=PlnUDQI1r6Q
2011年02月05日
面白いテレビ番組
(この記事は、書きかけていてしばらく放置していたのを、
手を加えて完成させたものです。)
なんだかんだ言っても、
最近面白いと感じたテレビ番組の多くは、
NHKの番組であった。
すでに放送が終了してしまったが、
NHK-BS2で放送した『総合診療医 ドクターG』は、
大変に面白かったし、非常に勉強になった。
僕のような鍼灸マッサージを生業としている者も、
独立開業しているかぎり総合診療医のような知識が必要だ。
もちろん、診断することはできない(医師法より)し、
診断できる程の知識は必要ないが、
「これは、大脳の検査ができる病院で診察してもことを勧めた方が良い」とか、
「この方は、心臓血管系の検査を受けることを勧めた方が良い」とか、
「よくわからないが、嫌な予感がするから総合病院で受診してもらおう」とか、
お客さんにとって危険な兆候を見逃さないために必要な情報が、
この番組にはあったと思う。
スポーツや運動をしている時の人の動きを観察するのが好きな僕は、
学生時代からダンス(舞踊)を観る機会が少なからずあり、
バレエにも興味を持っている。
NHK教育で放送している
『スーパーバレエレッスン
ロイヤル・バレエの精華 吉田都』は、
見ていて興味が尽きない番組だった。
吉田都さんが、若いバレエダンサー達を相手に
英国ロイヤル・バレエ団仕込みのレッスンを施すという趣向だが、
吉田都さんの動きや表現がすごいのである。
若いダンサーの踊りをまず観て、それから指導するのであるが、
観ることが主であまり動いていないはずの吉田都さんが、
ちょっとお手本をしてみせる時に
難しいであろう動きも簡単そうに「ヒョイ」っとやってしまい
少しのためらいや緊張もなく、
身体の軸のブレや動きの乱れもないのである。
体幹の使い方を学びつつ教える身としては、いろいろな意味で参考になった。
手を加えて完成させたものです。)
なんだかんだ言っても、
最近面白いと感じたテレビ番組の多くは、
NHKの番組であった。
すでに放送が終了してしまったが、
NHK-BS2で放送した『総合診療医 ドクターG』は、
大変に面白かったし、非常に勉強になった。
僕のような鍼灸マッサージを生業としている者も、
独立開業しているかぎり総合診療医のような知識が必要だ。
もちろん、診断することはできない(医師法より)し、
診断できる程の知識は必要ないが、
「これは、大脳の検査ができる病院で診察してもことを勧めた方が良い」とか、
「この方は、心臓血管系の検査を受けることを勧めた方が良い」とか、
「よくわからないが、嫌な予感がするから総合病院で受診してもらおう」とか、
お客さんにとって危険な兆候を見逃さないために必要な情報が、
この番組にはあったと思う。
スポーツや運動をしている時の人の動きを観察するのが好きな僕は、
学生時代からダンス(舞踊)を観る機会が少なからずあり、
バレエにも興味を持っている。
NHK教育で放送している
『スーパーバレエレッスン
ロイヤル・バレエの精華 吉田都』は、
見ていて興味が尽きない番組だった。
吉田都さんが、若いバレエダンサー達を相手に
英国ロイヤル・バレエ団仕込みのレッスンを施すという趣向だが、
吉田都さんの動きや表現がすごいのである。
若いダンサーの踊りをまず観て、それから指導するのであるが、
観ることが主であまり動いていないはずの吉田都さんが、
ちょっとお手本をしてみせる時に
難しいであろう動きも簡単そうに「ヒョイ」っとやってしまい
少しのためらいや緊張もなく、
身体の軸のブレや動きの乱れもないのである。
体幹の使い方を学びつつ教える身としては、いろいろな意味で参考になった。
2010年06月20日
筋は縮むことしかできない/筋の生理
前回、
「関節や筋肉に感じる痛みの多くは、その原因は筋肉にある」
と書きました。
ここで言う筋肉とは、骨格筋のことですが、
これから骨格筋(以後は単に筋と言う)の性質について書いてみます。
筋は、その内部に細長い筋繊維が数多く束になっていて、
これらの筋繊維が縮むことで力を生み出します。(※1)
ひとつひとつの筋は、他の筋と共同して縮み、
そこで生み出された力を利用して、
関節を固定したり、関節を動かしたりします。
言い換えると、
人が姿勢を保ったまま座っていたり立っていたりすることも
人が立ったり、歩いたり、走ったり、
その他様々な動きをすることも
すべて筋肉が縮んで生み出した力がなければ
不可能なのです。
筋は収縮して力を生み出します(※2)が、
逆に自分自身の長さを伸ばすことはできません。
一旦縮んだ筋が元の長さに戻るには、
その筋とはまったく反対の働きをする筋(拮抗筋と言う)が
収縮することで長くなるように引っ張られるか、
重力によって引っ張られるかしかありません。
例えば、上腕筋とか上腕二頭筋という筋は、
収縮すると肘を曲げます。
逆に肘を伸ばす上腕三頭筋が収縮すると肘が伸びるので、
上腕筋や上腕二頭筋は、
肘が伸びることによって引っ張られて、
元の長さに戻ることができます。
あるいは、肘を曲げた後、
腕の力を抜いてだらんと自然に下げれば、
重力によって肘が伸びます。
そのため、上腕筋や上腕二頭筋は
元の長さに伸びることができます。
このように、筋は自らが縮むことはできますが、
よそから引っ張られる力が働かないと
その長さを元のとおり伸ばすこともできないのです。
※1 筋繊維が縮むことで力を生み出す
厳密な説明を求める人には、この既述では満足しないかも知れません。
筋繊維は、細長くなった筋の細胞のことですが、
この筋繊維もその中に筋原線維というもっと細長いものが
束になって詰まっています。
筋原線維は、アクチンとミオシンと言う細長いタンパク質が
縦横に連なって出来ています。
アクチンとミオシンは、縦に交互に並んで連なっていますが、
この両者がお互いに重なり合うように
縦にスライドすることによって
力(張力)が発生します。
筋線維の中で、
集団としてのアクチンとミオシンが一斉にスライドして生み出した力が、
筋繊維の力であり、
筋線維の集団が生み出した力が、
筋の生み出した力であるというわけです。
(骨格筋の構造・筋線維の収縮)
アクチンとミオシンが重なるように縦にスライドするので
抵抗が強くなければ、普通は
アクチンとミオシンを合せた全体の長さは縮むわけで、
筋線維または筋全体も強い抵抗に合わなければ
普通は全体の長さが縮むので
「筋線維が縮むことで力を生み出」すと表現しました。
※2 筋は収縮して力を生み出す
この表現では、突然収縮と言う言葉を使っています。
生理学用語として厳密に使うと、
収縮という言葉は決して筋が縮むということを指していません。
「筋収縮とは、筋の張力が発生する意味であり、
必ずしも短縮を意味しない。」
(『基礎運動学 第4版』中村隆一・斎藤宏 著、医歯薬出版)
だそうです。
いきなり出てきた張力については後回しにするとして、
普通の方は収縮も短縮も「縮む」という意味だと思うでしょうね。
私も、とりあえずは
ほとんどそう言う意味合いで理解してもらってもいいかなと
そう思って使いました。
※1で説明したように、
アクチンとミオシンがスライドして力が生まれるので、
抵抗が強くなければ普通は収縮する時は「縮む」ので。
等尺性収縮とか伸張性収縮とか
筋が長さを縮めない収縮もあるのですが、
そこまで説明すると煩雑なので。
長さを縮めない収縮として上げた両者も、
アクチンとミオシンがスライドしようとする力が働いていることは確かなので、
少なくとも筋が力を発揮するということは
縮もうとする力(張力)を発揮しているということです。
筋収縮とは、筋の張力が発生することだから、
「筋は収縮して力を生み出す」という私の文は、
ひとつの事実を逆に言っているだけで、
まったく何の説明にもなっていないことになります。
学問的に正しい説明というのをやろうとすると、
手短かで簡単な説明になるわけではないので、
不正確(学問的には一部誤っている説明)だけど、
誰にでもわかりやすい、イメージし易い説明を
選ばざるを得ないということもあるんじゃないかと
そう考えてのことと理解して下さい。
少なくとも私の能力では、そうなってしまうということです。
「関節や筋肉に感じる痛みの多くは、その原因は筋肉にある」
と書きました。
ここで言う筋肉とは、骨格筋のことですが、
これから骨格筋(以後は単に筋と言う)の性質について書いてみます。
筋は、その内部に細長い筋繊維が数多く束になっていて、
これらの筋繊維が縮むことで力を生み出します。(※1)
ひとつひとつの筋は、他の筋と共同して縮み、
そこで生み出された力を利用して、
関節を固定したり、関節を動かしたりします。
言い換えると、
人が姿勢を保ったまま座っていたり立っていたりすることも
人が立ったり、歩いたり、走ったり、
その他様々な動きをすることも
すべて筋肉が縮んで生み出した力がなければ
不可能なのです。
筋は収縮して力を生み出します(※2)が、
逆に自分自身の長さを伸ばすことはできません。
一旦縮んだ筋が元の長さに戻るには、
その筋とはまったく反対の働きをする筋(拮抗筋と言う)が
収縮することで長くなるように引っ張られるか、
重力によって引っ張られるかしかありません。
例えば、上腕筋とか上腕二頭筋という筋は、

収縮すると肘を曲げます。
逆に肘を伸ばす上腕三頭筋が収縮すると肘が伸びるので、

上腕筋や上腕二頭筋は、
肘が伸びることによって引っ張られて、
元の長さに戻ることができます。
あるいは、肘を曲げた後、
腕の力を抜いてだらんと自然に下げれば、

重力によって肘が伸びます。
そのため、上腕筋や上腕二頭筋は
元の長さに伸びることができます。
このように、筋は自らが縮むことはできますが、
よそから引っ張られる力が働かないと
その長さを元のとおり伸ばすこともできないのです。
※1 筋繊維が縮むことで力を生み出す
厳密な説明を求める人には、この既述では満足しないかも知れません。
筋繊維は、細長くなった筋の細胞のことですが、
この筋繊維もその中に筋原線維というもっと細長いものが
束になって詰まっています。
筋原線維は、アクチンとミオシンと言う細長いタンパク質が
縦横に連なって出来ています。
アクチンとミオシンは、縦に交互に並んで連なっていますが、
この両者がお互いに重なり合うように
縦にスライドすることによって
力(張力)が発生します。
筋線維の中で、
集団としてのアクチンとミオシンが一斉にスライドして生み出した力が、
筋繊維の力であり、
筋線維の集団が生み出した力が、
筋の生み出した力であるというわけです。
(骨格筋の構造・筋線維の収縮)
アクチンとミオシンが重なるように縦にスライドするので
抵抗が強くなければ、普通は
アクチンとミオシンを合せた全体の長さは縮むわけで、
筋線維または筋全体も強い抵抗に合わなければ
普通は全体の長さが縮むので
「筋線維が縮むことで力を生み出」すと表現しました。
※2 筋は収縮して力を生み出す
この表現では、突然収縮と言う言葉を使っています。
生理学用語として厳密に使うと、
収縮という言葉は決して筋が縮むということを指していません。
「筋収縮とは、筋の張力が発生する意味であり、
必ずしも短縮を意味しない。」
(『基礎運動学 第4版』中村隆一・斎藤宏 著、医歯薬出版)
だそうです。
いきなり出てきた張力については後回しにするとして、
普通の方は収縮も短縮も「縮む」という意味だと思うでしょうね。
私も、とりあえずは
ほとんどそう言う意味合いで理解してもらってもいいかなと
そう思って使いました。
※1で説明したように、
アクチンとミオシンがスライドして力が生まれるので、
抵抗が強くなければ普通は収縮する時は「縮む」ので。
等尺性収縮とか伸張性収縮とか
筋が長さを縮めない収縮もあるのですが、
そこまで説明すると煩雑なので。
長さを縮めない収縮として上げた両者も、
アクチンとミオシンがスライドしようとする力が働いていることは確かなので、
少なくとも筋が力を発揮するということは
縮もうとする力(張力)を発揮しているということです。
筋収縮とは、筋の張力が発生することだから、
「筋は収縮して力を生み出す」という私の文は、
ひとつの事実を逆に言っているだけで、
まったく何の説明にもなっていないことになります。
学問的に正しい説明というのをやろうとすると、
手短かで簡単な説明になるわけではないので、
不正確(学問的には一部誤っている説明)だけど、
誰にでもわかりやすい、イメージし易い説明を
選ばざるを得ないということもあるんじゃないかと
そう考えてのことと理解して下さい。
少なくとも私の能力では、そうなってしまうということです。
2010年06月20日
筋肉の凝(こ)りと痛み
関節や筋肉などに感じる痛みは、
痛む部位の損傷(組織破壊)や骨格の異常
を意味しているのでしょうか?
必ずしもそうではありません。
身体をどこかに打ち付けたわけではないのに
激しい運動をしたわけでもないのに
いつの間にか関節や筋肉などが痛くなってくる。
肩や首の筋肉がすごく凝り、
すぐに肩や首が痛くなったり、
頭痛が起きたり、吐き気がしたり、めまいがしたりする。
腰が痛くて、
時には臀部(でんぶ:おしり)から大腿(だいたい:ふともも)にかけて
重苦しかったり痛くなったり、
中には膝裏や脛や足が痛くなったりしびれたりする。
これらは、これは、頸椎(けいつい:首の骨)や腰椎(ようつい:腰の骨)に
異常があるからでしょうか?
頸椎や腰椎のヘルニアが見つかる人もいますが、
見つからない人もいます。
見つかっても、症状のない人もいます。
骨の形に異常と小さな変形が見つかることもありますが、
原因と言い切るには疑問が残ることが多いようです。
そもそも、骨格に異常があると言うのなら、
何故、その症状に波があるのでしょうか?
何故、痛みのない時と痛む時があるのでしょうか?
癌などの腫瘍による痛み、
潰瘍・デキモノによる痛み、
内臓の病気による痛み又はその関連痛(原因は内臓だが体表の特定部位が痛む)、
ウイルスなどの感染による炎症の痛み、
骨折・脱臼・捻挫・打撲・肉離れなど外傷(がいしょう)による痛み、
心因性(しんいんせい)の痛みなどを除けば、
関節や筋肉に感じる痛みの多くは、
その原因は筋肉にあると言います。
その痛みの仕組みを詳しく説明しているサイトがあります。
加茂整形外科医院
初めての方は、このサイトの最初の表中の「筋痛症」や「筋骨格形の痛み」の初めの方、
「痛みからのメーッセージ」を読むことをお勧めします。
キーワード:筋痛症、筋筋膜性疼痛症候群、トリガーポイント
上記サイトに出てくる用語の解説としては、下を参照することをお勧めします。
■痛みとは
■痛みとは/□様々な痛み/(右の表)筋骨格(運動器)系の痛み/○筋肉痛
/筋筋膜性疼痛症候群:MPS
私は、上記のサイトでの主張を100%信じているわけではなく、
部分的には「そこまで言い切っちゃうのはどうかな?」
と思う部分もあります。
しかし、筋肉が原因となる痛みが多いのにそれが見過ごされていたり、
誤った見立てで民間治療が行なわれている現状を少しでも変える為に、
「論理的な根拠」を示すサイトとして紹介しました。
『身体の「ゆがみ」?』というタイトルのエントリーに書いたように
>ゆがみとは原因である前に、筋肉の引っぱりによる結果なのです。
>筋肉が必要以上に緊張し、硬くなっている状態、
>これこそが多くの問題を生んでいるのです。
身体の「ゆがみ」?
と考えています。
次は、筋肉の性質(生理)について解説してみたいと思います。
痛む部位の損傷(組織破壊)や骨格の異常
を意味しているのでしょうか?
必ずしもそうではありません。
身体をどこかに打ち付けたわけではないのに
激しい運動をしたわけでもないのに
いつの間にか関節や筋肉などが痛くなってくる。
肩や首の筋肉がすごく凝り、
すぐに肩や首が痛くなったり、
頭痛が起きたり、吐き気がしたり、めまいがしたりする。
腰が痛くて、
時には臀部(でんぶ:おしり)から大腿(だいたい:ふともも)にかけて
重苦しかったり痛くなったり、
中には膝裏や脛や足が痛くなったりしびれたりする。
これらは、これは、頸椎(けいつい:首の骨)や腰椎(ようつい:腰の骨)に
異常があるからでしょうか?
頸椎や腰椎のヘルニアが見つかる人もいますが、
見つからない人もいます。
見つかっても、症状のない人もいます。
骨の形に異常と小さな変形が見つかることもありますが、
原因と言い切るには疑問が残ることが多いようです。
そもそも、骨格に異常があると言うのなら、
何故、その症状に波があるのでしょうか?
何故、痛みのない時と痛む時があるのでしょうか?
癌などの腫瘍による痛み、
潰瘍・デキモノによる痛み、
内臓の病気による痛み又はその関連痛(原因は内臓だが体表の特定部位が痛む)、
ウイルスなどの感染による炎症の痛み、
骨折・脱臼・捻挫・打撲・肉離れなど外傷(がいしょう)による痛み、
心因性(しんいんせい)の痛みなどを除けば、
関節や筋肉に感じる痛みの多くは、
その原因は筋肉にあると言います。
その痛みの仕組みを詳しく説明しているサイトがあります。
加茂整形外科医院
初めての方は、このサイトの最初の表中の「筋痛症」や「筋骨格形の痛み」の初めの方、
「痛みからのメーッセージ」を読むことをお勧めします。
キーワード:筋痛症、筋筋膜性疼痛症候群、トリガーポイント
上記サイトに出てくる用語の解説としては、下を参照することをお勧めします。
■痛みとは
■痛みとは/□様々な痛み/(右の表)筋骨格(運動器)系の痛み/○筋肉痛
/筋筋膜性疼痛症候群:MPS
私は、上記のサイトでの主張を100%信じているわけではなく、
部分的には「そこまで言い切っちゃうのはどうかな?」
と思う部分もあります。
しかし、筋肉が原因となる痛みが多いのにそれが見過ごされていたり、
誤った見立てで民間治療が行なわれている現状を少しでも変える為に、
「論理的な根拠」を示すサイトとして紹介しました。
『身体の「ゆがみ」?』というタイトルのエントリーに書いたように
>ゆがみとは原因である前に、筋肉の引っぱりによる結果なのです。
>筋肉が必要以上に緊張し、硬くなっている状態、
>これこそが多くの問題を生んでいるのです。
身体の「ゆがみ」?
と考えています。
次は、筋肉の性質(生理)について解説してみたいと思います。
2010年06月20日
身体の「ゆがみ」?
お客さんによく聞かれるのが、
「からだが何処か、ゆがんでますか?」とか
「背骨がゆがんでいますか?」とか
「骨盤がゆがんでいますか?」とかいうことです。
あるいは、「◯◯で、骨盤(or背骨orからだ)がゆがんでいると言われたのですが、~。」
とおっしゃる方もよくいます。

(写真は本文中のお客さんとは関係ありません)
しかし、私には、背骨や骨盤や身体がゆがんでいるって、
「???」って感じで、意味がわかりません。
そこで、私がよく説明するのが、
「ゆがんでいるって言えば、ゆがんでいるかも知れません。
でも、そんなことは、問題ではありません。」ということ。
人の骨には、左右1対あるものがあるし、
脊柱(いわゆる背骨のこと)や仙骨や頭蓋骨のように、
左右の真ん中に位置するものもあります。
しかし、これら人の身体の骨で、
左右が鏡像のように完全な対象形なっているものはありません。
例えば頭蓋骨をみれば、
左右の目の穴も、顎の骨の左右の形も、
細かくみれば同じ形にはなっていません。
骨は、まったく形を変えないものではなく、
日々少しずつ細胞が入れ替わっているもので、
骨に力のかかる部位・大きさ・方向の違いによって
数週間・数ヶ月単位では形が変化するものなのです。
骨にかかる力とは、動かしたり支えたりする対象の重さであったり、
筋肉の引っ張る力だったりしますが、
人間は身体を左右対称に使ってはいないので、
右と左ではかかる力が違い、
それが骨の形の非対称性を生んでいるのです。
それに加えて骨を覆う筋肉の発達の違いによって、
なおさら左右の形の不均衡を生んでいます。
(顔の左右の中間に鏡を置いた時、
右顔面を映してできた顔と左顔面を映した顔とでは、
ずいぶんと違った顔になりますね。)
でも、それが普通の人間の身体なのです。
左右の不均衡を「ゆがみ」と言うのなら、
すべての人間は、ゆがんでいるのです。
私は、そんな小さなゆがみは問題ではないと考えます。
構造的に何らかの症状を引き起こす、
そんな「病的」なゆがみ以外は問題にする必要がありません。
私は、整形外科的に明確に脊柱側弯症と診断される
マラソンランナーを知っていました。
彼は、その身体であっても
日本の実業団のトップランナーで、
マラソンを2時間9分台で走ったことがあります。
ほとんどの日本人は、
脊柱側弯症ほどの「ゆがみ」を持っていません。
誰もが持っている小さな「ゆがみ」は、
骨格の構造が固定的に身体の機能異常を
引き起こすという代物ではありません。
一方、
筋肉や関節に、凝りや痛み、重苦しさなどを感じ、
姿勢や動きを見ると確かに左右バランスが悪い、
そんな身体の『ゆがみ』を感じさせる方も多いことは確かです。
しかし、その原因は、骨格系の異常(ゆがみ)であることは
少ないのです。
骨格はそれ自体は、動きもしないし力も生み出しません。
筋肉が働いて(収縮して)、
骨に力かかり、骨がその力を他へ伝えた時
初めて骨格(骨・関節)が動くのです。
個々の骨や関節の向きや位置は、
その時の筋肉の長さや引っ張る強さによって
初めて決まってくるのです。
骨格は勝手にゆがんだりしないのです。
ゆがみとは原因である前に、筋肉の引っぱりによる結果なのです。
筋肉が必要以上に緊張し、硬くなっている状態、
これこそが多くの問題を生んでいるのです。
(筋肉の緊張異常が生み出す問題については、
別の機会に書きたいと思います。)
どうか、「ゆがみ」という言葉に幻惑されないで下さい。
「からだが何処か、ゆがんでますか?」とか
「背骨がゆがんでいますか?」とか
「骨盤がゆがんでいますか?」とかいうことです。
あるいは、「◯◯で、骨盤(or背骨orからだ)がゆがんでいると言われたのですが、~。」
とおっしゃる方もよくいます。

(写真は本文中のお客さんとは関係ありません)
しかし、私には、背骨や骨盤や身体がゆがんでいるって、
「???」って感じで、意味がわかりません。
そこで、私がよく説明するのが、
「ゆがんでいるって言えば、ゆがんでいるかも知れません。
でも、そんなことは、問題ではありません。」ということ。
人の骨には、左右1対あるものがあるし、
脊柱(いわゆる背骨のこと)や仙骨や頭蓋骨のように、
左右の真ん中に位置するものもあります。
しかし、これら人の身体の骨で、
左右が鏡像のように完全な対象形なっているものはありません。
例えば頭蓋骨をみれば、
左右の目の穴も、顎の骨の左右の形も、
細かくみれば同じ形にはなっていません。
骨は、まったく形を変えないものではなく、
日々少しずつ細胞が入れ替わっているもので、
骨に力のかかる部位・大きさ・方向の違いによって
数週間・数ヶ月単位では形が変化するものなのです。
骨にかかる力とは、動かしたり支えたりする対象の重さであったり、
筋肉の引っ張る力だったりしますが、
人間は身体を左右対称に使ってはいないので、
右と左ではかかる力が違い、
それが骨の形の非対称性を生んでいるのです。
それに加えて骨を覆う筋肉の発達の違いによって、
なおさら左右の形の不均衡を生んでいます。
(顔の左右の中間に鏡を置いた時、
右顔面を映してできた顔と左顔面を映した顔とでは、
ずいぶんと違った顔になりますね。)
でも、それが普通の人間の身体なのです。
左右の不均衡を「ゆがみ」と言うのなら、
すべての人間は、ゆがんでいるのです。
私は、そんな小さなゆがみは問題ではないと考えます。
構造的に何らかの症状を引き起こす、
そんな「病的」なゆがみ以外は問題にする必要がありません。
私は、整形外科的に明確に脊柱側弯症と診断される
マラソンランナーを知っていました。
彼は、その身体であっても
日本の実業団のトップランナーで、
マラソンを2時間9分台で走ったことがあります。
ほとんどの日本人は、
脊柱側弯症ほどの「ゆがみ」を持っていません。
誰もが持っている小さな「ゆがみ」は、
骨格の構造が固定的に身体の機能異常を
引き起こすという代物ではありません。
一方、
筋肉や関節に、凝りや痛み、重苦しさなどを感じ、
姿勢や動きを見ると確かに左右バランスが悪い、
そんな身体の『ゆがみ』を感じさせる方も多いことは確かです。
しかし、その原因は、骨格系の異常(ゆがみ)であることは
少ないのです。
骨格はそれ自体は、動きもしないし力も生み出しません。
筋肉が働いて(収縮して)、
骨に力かかり、骨がその力を他へ伝えた時
初めて骨格(骨・関節)が動くのです。
個々の骨や関節の向きや位置は、
その時の筋肉の長さや引っ張る強さによって
初めて決まってくるのです。
骨格は勝手にゆがんだりしないのです。
ゆがみとは原因である前に、筋肉の引っぱりによる結果なのです。
筋肉が必要以上に緊張し、硬くなっている状態、
これこそが多くの問題を生んでいるのです。
(筋肉の緊張異常が生み出す問題については、
別の機会に書きたいと思います。)
どうか、「ゆがみ」という言葉に幻惑されないで下さい。