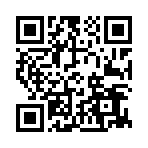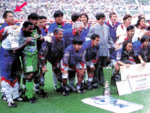2010年06月20日
筋は縮むことしかできない/筋の生理
前回、
「関節や筋肉に感じる痛みの多くは、その原因は筋肉にある」
と書きました。
ここで言う筋肉とは、骨格筋のことですが、
これから骨格筋(以後は単に筋と言う)の性質について書いてみます。
筋は、その内部に細長い筋繊維が数多く束になっていて、
これらの筋繊維が縮むことで力を生み出します。(※1)
ひとつひとつの筋は、他の筋と共同して縮み、
そこで生み出された力を利用して、
関節を固定したり、関節を動かしたりします。
言い換えると、
人が姿勢を保ったまま座っていたり立っていたりすることも
人が立ったり、歩いたり、走ったり、
その他様々な動きをすることも
すべて筋肉が縮んで生み出した力がなければ
不可能なのです。
筋は収縮して力を生み出します(※2)が、
逆に自分自身の長さを伸ばすことはできません。
一旦縮んだ筋が元の長さに戻るには、
その筋とはまったく反対の働きをする筋(拮抗筋と言う)が
収縮することで長くなるように引っ張られるか、
重力によって引っ張られるかしかありません。
例えば、上腕筋とか上腕二頭筋という筋は、
収縮すると肘を曲げます。
逆に肘を伸ばす上腕三頭筋が収縮すると肘が伸びるので、
上腕筋や上腕二頭筋は、
肘が伸びることによって引っ張られて、
元の長さに戻ることができます。
あるいは、肘を曲げた後、
腕の力を抜いてだらんと自然に下げれば、
重力によって肘が伸びます。
そのため、上腕筋や上腕二頭筋は
元の長さに伸びることができます。
このように、筋は自らが縮むことはできますが、
よそから引っ張られる力が働かないと
その長さを元のとおり伸ばすこともできないのです。
※1 筋繊維が縮むことで力を生み出す
厳密な説明を求める人には、この既述では満足しないかも知れません。
筋繊維は、細長くなった筋の細胞のことですが、
この筋繊維もその中に筋原線維というもっと細長いものが
束になって詰まっています。
筋原線維は、アクチンとミオシンと言う細長いタンパク質が
縦横に連なって出来ています。
アクチンとミオシンは、縦に交互に並んで連なっていますが、
この両者がお互いに重なり合うように
縦にスライドすることによって
力(張力)が発生します。
筋線維の中で、
集団としてのアクチンとミオシンが一斉にスライドして生み出した力が、
筋繊維の力であり、
筋線維の集団が生み出した力が、
筋の生み出した力であるというわけです。
(骨格筋の構造・筋線維の収縮)
アクチンとミオシンが重なるように縦にスライドするので
抵抗が強くなければ、普通は
アクチンとミオシンを合せた全体の長さは縮むわけで、
筋線維または筋全体も強い抵抗に合わなければ
普通は全体の長さが縮むので
「筋線維が縮むことで力を生み出」すと表現しました。
※2 筋は収縮して力を生み出す
この表現では、突然収縮と言う言葉を使っています。
生理学用語として厳密に使うと、
収縮という言葉は決して筋が縮むということを指していません。
「筋収縮とは、筋の張力が発生する意味であり、
必ずしも短縮を意味しない。」
(『基礎運動学 第4版』中村隆一・斎藤宏 著、医歯薬出版)
だそうです。
いきなり出てきた張力については後回しにするとして、
普通の方は収縮も短縮も「縮む」という意味だと思うでしょうね。
私も、とりあえずは
ほとんどそう言う意味合いで理解してもらってもいいかなと
そう思って使いました。
※1で説明したように、
アクチンとミオシンがスライドして力が生まれるので、
抵抗が強くなければ普通は収縮する時は「縮む」ので。
等尺性収縮とか伸張性収縮とか
筋が長さを縮めない収縮もあるのですが、
そこまで説明すると煩雑なので。
長さを縮めない収縮として上げた両者も、
アクチンとミオシンがスライドしようとする力が働いていることは確かなので、
少なくとも筋が力を発揮するということは
縮もうとする力(張力)を発揮しているということです。
筋収縮とは、筋の張力が発生することだから、
「筋は収縮して力を生み出す」という私の文は、
ひとつの事実を逆に言っているだけで、
まったく何の説明にもなっていないことになります。
学問的に正しい説明というのをやろうとすると、
手短かで簡単な説明になるわけではないので、
不正確(学問的には一部誤っている説明)だけど、
誰にでもわかりやすい、イメージし易い説明を
選ばざるを得ないということもあるんじゃないかと
そう考えてのことと理解して下さい。
少なくとも私の能力では、そうなってしまうということです。
「関節や筋肉に感じる痛みの多くは、その原因は筋肉にある」
と書きました。
ここで言う筋肉とは、骨格筋のことですが、
これから骨格筋(以後は単に筋と言う)の性質について書いてみます。
筋は、その内部に細長い筋繊維が数多く束になっていて、
これらの筋繊維が縮むことで力を生み出します。(※1)
ひとつひとつの筋は、他の筋と共同して縮み、
そこで生み出された力を利用して、
関節を固定したり、関節を動かしたりします。
言い換えると、
人が姿勢を保ったまま座っていたり立っていたりすることも
人が立ったり、歩いたり、走ったり、
その他様々な動きをすることも
すべて筋肉が縮んで生み出した力がなければ
不可能なのです。
筋は収縮して力を生み出します(※2)が、
逆に自分自身の長さを伸ばすことはできません。
一旦縮んだ筋が元の長さに戻るには、
その筋とはまったく反対の働きをする筋(拮抗筋と言う)が
収縮することで長くなるように引っ張られるか、
重力によって引っ張られるかしかありません。
例えば、上腕筋とか上腕二頭筋という筋は、

収縮すると肘を曲げます。
逆に肘を伸ばす上腕三頭筋が収縮すると肘が伸びるので、

上腕筋や上腕二頭筋は、
肘が伸びることによって引っ張られて、
元の長さに戻ることができます。
あるいは、肘を曲げた後、
腕の力を抜いてだらんと自然に下げれば、

重力によって肘が伸びます。
そのため、上腕筋や上腕二頭筋は
元の長さに伸びることができます。
このように、筋は自らが縮むことはできますが、
よそから引っ張られる力が働かないと
その長さを元のとおり伸ばすこともできないのです。
※1 筋繊維が縮むことで力を生み出す
厳密な説明を求める人には、この既述では満足しないかも知れません。
筋繊維は、細長くなった筋の細胞のことですが、
この筋繊維もその中に筋原線維というもっと細長いものが
束になって詰まっています。
筋原線維は、アクチンとミオシンと言う細長いタンパク質が
縦横に連なって出来ています。
アクチンとミオシンは、縦に交互に並んで連なっていますが、
この両者がお互いに重なり合うように
縦にスライドすることによって
力(張力)が発生します。
筋線維の中で、
集団としてのアクチンとミオシンが一斉にスライドして生み出した力が、
筋繊維の力であり、
筋線維の集団が生み出した力が、
筋の生み出した力であるというわけです。
(骨格筋の構造・筋線維の収縮)
アクチンとミオシンが重なるように縦にスライドするので
抵抗が強くなければ、普通は
アクチンとミオシンを合せた全体の長さは縮むわけで、
筋線維または筋全体も強い抵抗に合わなければ
普通は全体の長さが縮むので
「筋線維が縮むことで力を生み出」すと表現しました。
※2 筋は収縮して力を生み出す
この表現では、突然収縮と言う言葉を使っています。
生理学用語として厳密に使うと、
収縮という言葉は決して筋が縮むということを指していません。
「筋収縮とは、筋の張力が発生する意味であり、
必ずしも短縮を意味しない。」
(『基礎運動学 第4版』中村隆一・斎藤宏 著、医歯薬出版)
だそうです。
いきなり出てきた張力については後回しにするとして、
普通の方は収縮も短縮も「縮む」という意味だと思うでしょうね。
私も、とりあえずは
ほとんどそう言う意味合いで理解してもらってもいいかなと
そう思って使いました。
※1で説明したように、
アクチンとミオシンがスライドして力が生まれるので、
抵抗が強くなければ普通は収縮する時は「縮む」ので。
等尺性収縮とか伸張性収縮とか
筋が長さを縮めない収縮もあるのですが、
そこまで説明すると煩雑なので。
長さを縮めない収縮として上げた両者も、
アクチンとミオシンがスライドしようとする力が働いていることは確かなので、
少なくとも筋が力を発揮するということは
縮もうとする力(張力)を発揮しているということです。
筋収縮とは、筋の張力が発生することだから、
「筋は収縮して力を生み出す」という私の文は、
ひとつの事実を逆に言っているだけで、
まったく何の説明にもなっていないことになります。
学問的に正しい説明というのをやろうとすると、
手短かで簡単な説明になるわけではないので、
不正確(学問的には一部誤っている説明)だけど、
誰にでもわかりやすい、イメージし易い説明を
選ばざるを得ないということもあるんじゃないかと
そう考えてのことと理解して下さい。
少なくとも私の能力では、そうなってしまうということです。
Posted by からだが資本 at 19:55│Comments(0)
│人の身体について